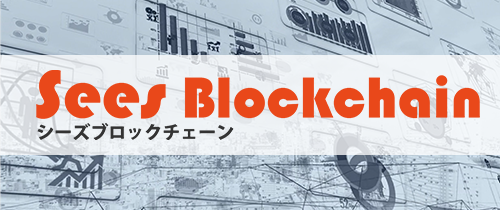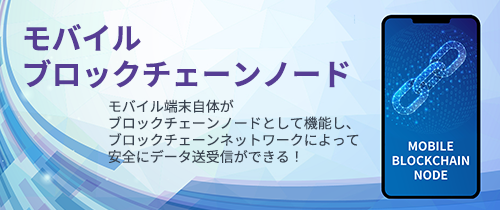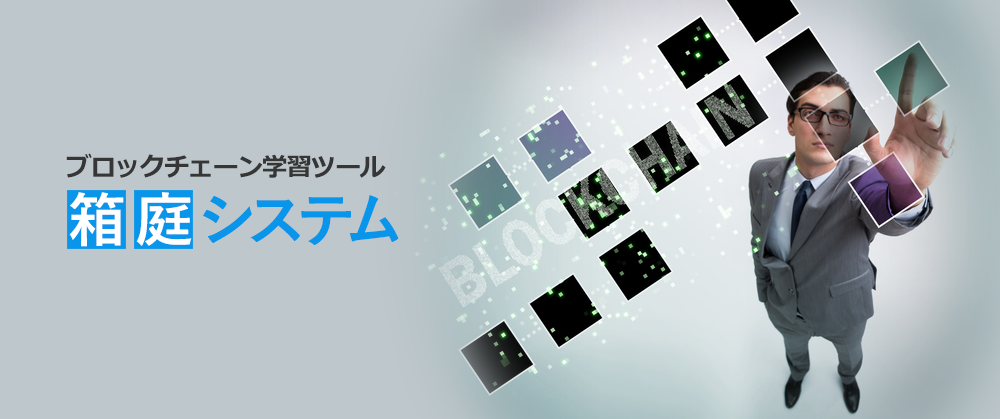ブロックチェーンの黎明
ブロックチェーンとはビットコインの誕生によって広く世間に知られるようになった電子取引に使われる暗号技術の一つです。
暗号通貨による電子取引の概念は、サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)が2008年初頭からmetzdowd.com内の暗号理論に関するメーリングリスト「暗号通貨に関する論文」を発表したことから始まりました。
サトシ・ナカモト論文を要約すると、「インターネット上の商取引は例外なく電子取引を処理し信用できる第三者機関としての金融機関に頼っていることが現状である。 金融機関は争いの仲裁を行うために完全に非可逆的な取引は扱わない。 仲裁コストが取引コストを引き上げるため少額取引の可能性は失われる。 必要なのは第三者機関を介さずに当事者同士が直接取引を行えることである。 その場合、信頼ではなく暗号技術に基づいた決裁システムがあればよい。 暗号通貨を多重に使用されるような不正から守るためにP2P分散タイムスタンプサーバーを利用する。 善良なノードが悪意あるノードよりもCPU能力が上回っていればシステムはセキュリティ的に安全である」というものです。
この論文には、金融機関などの仲裁者を通さずに直接当事者間でインターネット上において正常な取引を行えるシステムとして具体的なシステムデザインが示されています、これがその後に確立された世にいうブロックチェーンと呼ばれる電子取引システムなのです。
2009年1月、サトシ・ナカモトの論文にあるブロックチェーン技術を用いて複数のコンピューター提供者との間で分散処理による取引システムを構築し、そのうえで取引される通貨として世界初の暗号通貨である「ビットコイン」が誕生しました。
ブロックチェーン技術の基礎
ブロックチェーンの特徴は大きく分けて3つあげられます。
最初に断っておきますと「ブロックチェーン=暗号通貨」ではありません、暗号通貨は単にブロックチェーンのDApps(分散アプリケーション)の一つでしかありません。
技術カテゴリ的にブロックチェーンの特徴は以下の3つに絞られます。
- 1.自律分散システム(P2Pネットワーク)
- 2.暗号技術(ハッシュ関数)
- 3.コンセンサスアルゴリズム(取引の合意)
世に存在する暗号通貨におけるブロックチェーンはこれまで解明されてこなかった分散システム上の課題を解決しているのではないかと多くの機関が検証に乗り出しています、暗号通貨の技術として導入されたブロックチェーンですが暗号通貨はその技術の利用分野の一つに過ぎません。
今では金融機関のみならず、医療現場やIoT分野(ネットワークで機械を遠隔操作する技術)にまで応用できる技術として注目されています。
ただし少なくても暗号通貨に応用されているブロックチェーンの正当性を裏付けているものはビットコインのたった十数年間の「未停止」という運用実績だけです、しかし逆説的に言うと「ブロックチェーン自体は過去一度もハッキングされたり停止したりしていない」という完全なシステムであるといえます、時に暗号通貨の不正流出がニュースになりますが、これはブロックチェーン自体が乗っ取られたのではなくブロックチェーンに接続されたユーザー端末が乗っ取られたために起きた問題です。
ここでブロックチェーン技術は理論的に第三者によって検証され確立されたものではないというのが極めて重要になります、つまりブロックチェーン技術によって誕生した分散アプリケーションの一つである暗号通貨は今も尚、多くの技術者によって改善が繰り返されている進化の過程にあるのです。
それではブロックチェーン技術の主要3項目について説明していきます。
自律分散システム(P2Pネットワーク)
自律分散システムでいうP2P(Peer to Peer)とは、複数の端末が接続されたネットワーク上でそれぞれの端末同士が通信を直接行うというスタイルであり、管理者サーバーが一切存在しないネットワーク接続を意味します。
通常の金融システムでは高いセキュリティを施した中央処理サーバーが権限を持ち運営されるため多大なコストがかかるという問題があります、対して暗号通貨に代表されるパブリック型のブロックチェーンは中央処理サーバーによる中央権限型ではなく特定の端末に権限を集中させない非中央集権型の自律分散型P2Pネットワークを構築し運用することを前提にしています。
この非中央集権型ネットワークはコストがかからず透明性を維持できるとされています、ではなぜ金融システムや他のシステムで自律分散型ネットワークが構築されてこなかったのでしょうか?
それは一つの解決できない大きな問題が存在しているためです、その大きな問題とは「ビザンチン将軍問題」というネットワークにおいて故障または故意によって嘘の情報が伝達される可能性がある場合にそのネットワーク内で正しい合意を形成できるかという問題です。
この問題に対してビットコインはPoW(Proof of Work)というコンセンサスアルゴリズムによって解決を試みています、PoWとは自律分散型ネットワーク内で行われる取引の正当性をマイニング(採掘)という複数のノードの承認を取り入れることによって正当性を示そうとするものです。
この承認方法は莫大なコンピューター処理能力を必要とする計算そのものであり、この作業に時間的且つ経済的負担をかけさせることによって悪意ある攻撃を防ぐシステムを構築しているのです、そしてこの作業こそが電子署名とハッシュ関数を使った暗号化技術によるものなのです。
対して管理者が介入するコンソーシアム型のブロックチェーンはあくまでも管理者を置いた電子取引台帳だけをブロックチェーン化したもので、その運用においては必ず管理者が介在しユーザー同士の自律分散型P2P取引を行えない用途に適応しています、したがって取引の正当性を示すためのマイニング処理は不要となります。
その代わりとして取引の正当性を担保する独自のコンセンサスアルゴリズムが存在しています。
また産業用途として普及しつつあるプライベート型ブロックチェーンでは更に柔軟なシステムになっており、取引の正当性を担保するためにセルフマイニング方式を採用しています。
このプライベート型ブロックチェーンは運営者が存在していても取引においては自律分散型P2P取引が行えるという極めて優れたブロックチェーンとして現在大いに注目されています。
近年になりプライベート型ブロックチェーンは「産業用途ブロックチェーン」、または「エンタープライズ・ブロックチェーン」と呼ばれるようになりました。
株式会社シーズは、このプライベート型ブロックチェーンにIoTやM2M(Machine to Machine)における高度なデータセキュリティ・ソリューションとしてあらゆる分野に応用することを目的に、2016年より独自方式のプライベートブロックチェーンの研究を開始し2018年にシーズブロックチェーンが産声をあげたのです。
暗号技術(ハッシュ関数)
ブロックチェーンは、電子署名とハッシュ関数の数珠繋ぎ(じゅずつなぎ)という暗号技術によって改ざんされることを防止しています。
電子取引台帳を収めたブロックがハッシュ関数のサンドウィッチ方式で数珠繋ぎになっているので、その構造からブロックチェーンという名称で呼ばれるようになりました。
例えばあるブロックが形成されると、それまでの取引全てを要約したデータ(ハッシュ値)がハッシュ関数によって生成されます。
次に生成されるブロックは要約データと取引データを含んだもので形成され、次のブロックではそれらの要約データが生成されます。
このように一つのブロックにすべての取引データの要約データが入っているため、不正を行うためには改ざんした取引以降のすべてのブロックを作り直さなければなりません。
加えてコンセンサスアルゴリズム(参加者による合意)により、より早く計算結果を出したものがブロックの生成権利を獲得するように作られています。
つまり改ざんを行うには他のノードよりも早く計算しなければならず、莫大な計算能力を有するコンピューターを複数台並列使用しなければなりません、これがブロックチェーンの改ざんは不可能であるという仕組みの根拠なのです。
この技術はブロックチェーンの安全性・透明性・トレーサビリティを正当に謳える根拠でありキーテクノロジーともなっています。
コンセンサスアルゴリズム(取引の合意)
ビットコインでは、PoWというコンセンサスアルゴリズムによって電子取引内容を保障するという方法を採用しています。
取引データを含むブロックを生成するためにはハッシュ関数によるハッシュ値が必要になります、これを生成するためには前ブロックのハッシュ値からただ一つ導き出されるナンス(数値)を難解な計算により取得し、そのナンスを用いて次のブロックのハッシュ値を形成しなければなりません。
このナンスを一番早く見つけたノードだけが次のブロックを生成することが可能となります、ビットコインではこの計算が約10分で完結するように計算難易度を調整しています。
またビットコインではこれらのブロックが長く続いているチェーンを採用するため、改ざんしてブロックを生成することは通常より遥かに多くの計算能力と時間を有することになり現実的には極めて困難であるとしています。
ただし、存在する良心的なマイナー以上に悪意を持ったマイナー、または巨大な計算能力を持ったマイナーが存在すると能力的に悪意のある者が上回ってしまうため、これらのシステムは簡単に崩壊してしまう危険性があります。
暗号通貨におけるパブリック型ブロックチェーンに対して産業用途のプライベート型ブロックチェーンではセルフマイニングという方法によって取引の妥当性を保障しています。
このセルフマイニングとは管理サーバーを複数台用意して、その複数の管理サーバー間だけで代表制によるマイニングを行わせています、この方式はシーズブロックチェーンでも採用しているコンセンサスアルゴリズムであり、代表制マイニング=複数ノードによるセルフマイニングとして独自方式を確立しています。
これによって、実際には管理者は不在でもユーザー同士は取引内容が保障されたうえで自律分散型P2P取引を安心して行うことができます。
シーズブロックチェーンはこのように進化したプライベート型ブロックチェーンであり、P2P取引を自動化させ尚且つ取引内容を保障できるという未来志向型の優れたブロックチェーンなのです。
ビザンチン将軍問題とは
ここで余談ですが、P2Pネットワークが抱える問題としてネットワーク発症時から度々課題となってきた「ビザンチン将軍問題」について簡単に触れることにします。
悪意のある者がネットワーク内に存在する場合にどのようにして正しい取引を承認するかという問題は、「ビザンチン将軍問題」として分散システムを構築する上で長い間大きな課題とされてきました。
この「ビザンチン将軍問題」というのは、「敵国を囲む複数の将軍間で一斉攻撃の作戦の合意を取らなくてはならないシーンで、味方の将軍の中に裏切り者がいたり、伝令者が捕まったり、偽の情報を流されたりする可能性がある場合にどのようにして正しい情報を判断し全員の合意を取るか」というものです。
インターネット上においてもハッカーに代表されるように、悪意のある者は必ず存在し且つ通信環境も完全なものは存在せず不安定なものです。
例えば、インターネットで2者間の合意を得る「2人の将軍問題」というのが「ビザンチン将軍問題」とは別に存在しています。
これは現在ネットワークの世界標準通信プロトコルであるTCP/IP(インターネット・プロトコル・スイート)が完全に解決しているとされています、しかし世の中には完全なロジックやITシステムは存在しないのです。
例えばネットワークの世界標準通信プロトコルであるTCP/IPにしても2者のコンピューターが同時にハッキングされた場合はこれを検出できる方法は皆無であり、何事も無かったかのように2者は不正な通信を正常な通信と変わることなく継続してしまうのです。
このような状況下で他のノードが同じ正しい情報をもとに合意できるかという問題が分散システムを構築する上では古くから課題となっていました。
しかし、実際にビットコインが分散システムによって長期間維持されていることを見て「ビットコインがビザンチン将軍問題を解決している」と言われるようになりました。
しかし、実態には解決しているのではなく「悪意のある存在がいても50%以上の計算能力がなければ支配されることはない」という推測理論によるものでしかありません。
近年の研究では41%の計算能力でも1/2の確率で新たなブロックを生成できることが示されています。
結論としてはビットコインをはじめ、世の中にある分散処理システムは「ビザンチン将軍問題」を解決していない、むしろその問題を解決しなくてもよい方法を見つけ出し「避けて通っている」というのが正解なのです。
対して、シーズブロックチェーンは産業用途を意識して理想的且つ最適にデザインされたプライベート型ブロックチェーンであり、複数の管理サーバーによる代表制マイニングという独自のコンセンサスアルゴリズムを採用しています。
ただ全てが自社サーバーで運用しているから中央集権型でありブロックチェーンではないという人もいます、しかしプライベート型ブロックチェーンはデータセキュリティを担保しながら取引を保証する技術的解決法としては極めて優れたものであり、第三者を介さずに取引を保障したうえで自律分散P2P取引を有効にし、尚且つ伝送されるデータのセキュリティを極限まで高めているのです。
非中央集権型ではないからブロックチェーンではないという明確な定義がされるならシーズブロックチェーンは世に言うブロックチェーンではなく、進化型のデータセキュリティシステムということでよいと思うのです。
プライベート型ブロックチェーンの管理サーバーは人による管理者を必要としません、パブリック型のマイニングを複数の代表サーバー(ノード)の相互の分散技術によって自動で行わせているのです。
「限られたノードにだけマイニング権利を与えている」、ここからプライベート型ブロックチェーンと呼ばれているのです、そこで行われていることはパブリック型のブロックチェーンにおけるコンセンサスと何も変わるものではありません。
何故ブロックチェーンは安全だと言えるのか
何故ビットコインはいままでシステムダウンすることなく正常に運営し続けることが出来ているのでしょうか、それは悪意を持つ者たちの根拠が経済的理由だった場合にシステムを乗っ取ったとしても「利を得ない」状況にしているためです。
ビットコインは、ネットワークに参加するすべてのノード(システムを構成するサーバーや参加者のコンピューター端末)に対してマイニングの報酬を与えています。
マイニングの競争を勝ち抜くためには他のノードよりも早い計算能力を持つコンピューターを用意する必要があり、さらにそれを運用する電気代などの設備やランニングコストといった経済的負担が伴うことになります。
多くのマイナー達がそれぞれの計算能力を駆使してマイニングを行っているため、参加者全員の50%を超える処理能力を持つコンピューターとその運用にはマイニングの報酬以上にコストがかかってしまうのです。
その10分という計算の難易度とビットコインの報酬のバランスなどを総合的に考えた場合、悪意のある参加者にとって「利を得ない」結果を齎すことによって安全を何とか確保しているということに過ぎないのです。
また、他のパブリック型ブロックチェーンではビットコインのPoW(Proof of Work)に代わり、PoS(Proof of Status)やPoI(Proof of Importance)というコンセンサスアルゴリズムを用いて所有数や貢献度を自動で分析して報酬を支払うことにより不正を働くよりも協力する方に利が有るという状況を作り出し安全に運営しようとしています。
シーズブロックチェーンに代表される産業用途のプライベート型ブロックチェーンでは悪意の第三者に乗っ取られるという脅威は皆無です、それは代表制のノードによってセルフマイニングを行っているからに他なりません。
したがって産業用途に考えられたプライベート型ブロックチェーンは最も効率且つセキュリティ性の高いブロックチェーンであると言えるのです。
セルフマイニングは独自のアルゴリズムを用いており極めて高速に取引を行うことが可能です、ちなみにIoTへの応用においては数m秒での伝送を実現させています。
ブロックチェーンは伝送に時間がかかるというのはマイニングを行うパブリック型ブロックチェーンでの話でありプライベート型ブロックチェーンには適用されません。
パブリック型ブロックチェーンが抱える課題
ビットコインに限らず世に存在するパブリック型ブロックチェーン全般に言えることですが、マイニングによる報酬や貢献度に応じた報酬による不正防止策は不正をすることによって利を得たいという者たちにしか通用しない施策です。
電子取引システムの混乱や破壊のみを目的とし経済的価値も鑑みない悪意を持った者が存在する場合には、例えパブリック型ブロックチェーンであっても故意に破壊もしくは支配される可能性を否定できません、世界的に流通しているビットコインを始めとした暗号通貨の崩壊は今や経済に多大な影響を与える結果を生んでしまうでしょう。
ビットコインのブロックチェーンはすべての取引データが参加者ノードに分散記録されていますが50%以上の計算能力をもつ悪意のある参加者によってこの全てが書き換えられてしまう可能性は否定できません。
管理する権限を持つ者がいないがために改ざんが発見されたとしても、それをリカバリーすることができないのが事実として存在しています。
また新たなロジックを追加したパブリック型ブロックチェーンが誕生した際に、ビットコインなどでノウハウを蓄積した参加者が新しいパブリック型ブロックチェーンのマイニングに参加し圧倒的な計算能力で一瞬にして支配してしまうことも想定できます、所謂マイニングを世界的な大組織で行う巨大マイナープールの存在がその一つです。
このようにビットコインを始めとした現存するパブリック型ブロックチェーンは「ビザンチン将軍問題」を解決しているとは言えず、たまたま上手く稼働させているに過ぎないシステムであり、いつシステムが崩壊や支配されてもおかしくない状態にあるということが最大の課題となっているのです。
何度も対比として出している産業用途のプライベート型ブロックチェーンではこういった脅威は皆無となります。
産業用途ブロックチェーンの台頭
世の中にはパブリック型ブロックチェーンによる非中央集権型取引システムを疑問も持たずに支持する人で溢れかえっています、かのアインシュタインは「疑問を持たずに敬意を表するのは事実に対する最大の冒涜である」というけだし名言を残しています。
この名言が示すようにIT技術を熟知した人の多くはパブリック型ブロックチェーンに多くの危険性を見出しています、金融機関も近年ブロックチェーンによる取引を行い始めていますが、全てが中央集権によるコンソーシアム型のブロックチェーンを採用している事実を見ても一目瞭然です。
「人件費などのコストが少なく透明性がある」、実はこのパブリック型ブロックチェーンの優位点こそが最大の欠点でもあるのです。
パブリック型ブロックチェーンの危惧する問題の一つには確かにノードにおける台帳の安全性は担保されているかのように見えます、しかし例えばユーザーの端末が突然故障した場合にはパスワードなどのアクセスキーをバックアップしていなければ取引台帳はノード間で保障されていても取引することはできなくなり、事実上保有資産は失われることになります。
更には端末がハッキングされウォレットが盗用された場合も同じことです、この問題を現在パブリック型ブロックチェーンでは全く解決の糸口さえ見つけることができません。
もう一つはスケーラビリティというブロックチェーンの取引規模の変化に対する柔軟性への対応です、今やビットコインは世界中で利用されており店舗での支払いや労働報酬の支払いなどにも利用され始めてきていますが、その取引速度の遅さが問題であり決裁までに数時間を有する場合も発生しています。
この問題の対応策としてビットコインの原論文(Satoshi Nakamoto, 2008)に記載されていながら、いまだ実装されていないSegwit(Segrageted witness)と呼ばれる技術を開発者側が導入しようとしました。
これはブロックチェーンの容量を見かけ上増やすもので電子署名部分をブロックから分離して管理するという、今までの仕様と互換性を保ちながら行えるというシステムの上位互換性のあるアップデートです。
対して、世界最大のマイニンググループであるAntPoolが支持したのはブロックチェーンの1ブロック単位のトランザクション容量そのものを増やしてしまおうという解決策です。
ビットコインのブロックチェーンのブロックは約3,000の取引記録が納められその容量が1MBと決められています、この容量を8MBにまで増加させようというものですが今までの仕様で作られてきたブロック(取引台帳)は反映されず事実上全く新しいブロックチェーンができることになってしまうのです。
前者の互換性を持ったままでアップデートを行うことを「ソフトフォーク」、後者の新しい仕様でブロックチェーンを作ってしまうことを「ハードフォーク」といい、パブリック型ブロックチェーンはソフトフォークとハードフォークの対立が起こることは否めません。
事実ビットコインと同じ問題がイーサリアムで過去起きており、イーサリアムではハードフォークにより2つのブロックチェーンに分裂してしまいました。
このように技術的に避けて通れない課題、そして中央集権を持たないことで起きうる大きな保障問題、これら全てを熟知した人であれば簡単に非中央集権型であるパブリック型ブロックチェーンが優れているとは言えないのではないでしょうか?
ここでも最後に追記しておきますが、限られたノードだけでコンセンサスを行えるプライベート型ブロックチェーンは事実上の運営者が存在しています、管理サーバーも実在しスケーラビリティ問題や各種のメンテナンスにおいて高い安全性と運用を保障できるようになっています。
社会に浸透する新時代における産業用途のブロックチェーンは、シーズブロックチェーンに代表されるP2P取引が安全に行えるだけでなく、拡張などの不安が皆無であるプライベート型に集約して行くのは必然だと言えるでしょう。
2018年6月公開
2025年9月更新
株式会社シーズ
代表取締役会長 伊東久雄
Back to Top